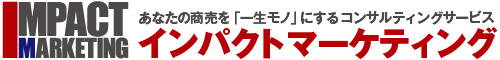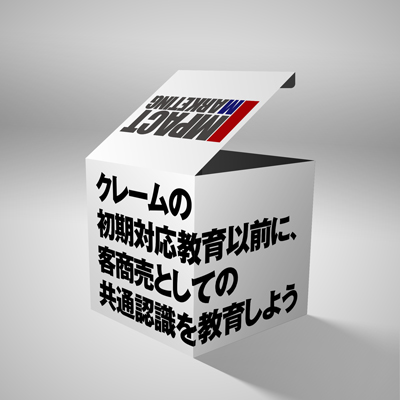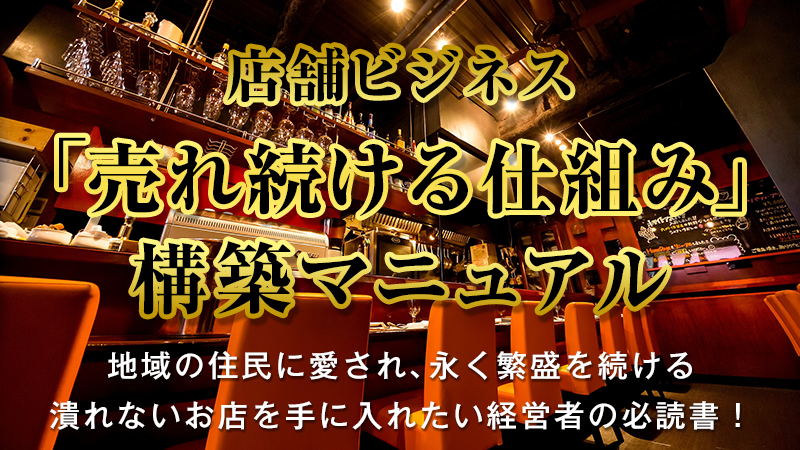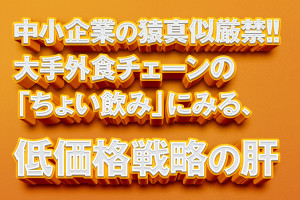クレームの初期対応教育以前に、客商売としての共通認識を教育しよう
スポンサーリンク
どもっ!商売力養成コンサルタントの福谷です。
久しぶりに、ひどいクレーム対応を受けたのでシェアします(笑)
このケース、お客様がわかりやすくキレたりしない限り、売り手側はコトの重大さに気付き難いというリスクがあるので要注意です。
私は先日AとB、ふたつの商品を購入したんですが、届いて開封したらAが入っておらず代わりにCが入っていました。
伝票にはAと明記されていたので、たぶん注文商品を取り揃えて出荷する際の、ピッキング作業での確認ミスではないかと思います。
で、仕方なく伝票に記載されている番号に電話。
最初に出た若い男性に一通りの状況を説明すると、謝罪らしき言葉も特に無いまま「担当者におつなぎします」とのこと。
オマエちゃうんかい!! と心でツッコミながらも一旦保留になり、すぐ若い女性が電話に。
担当者「はい、お電話代わりました●●です」
私「はい」
担当者「……………………」
私「……………………」
担当者「……………………」
私「……………………」
ん? 何も言わんの? 何も尋ねんの?
担当者「……………………」
私「……………………」
担当者「………………………、え?」
え? やあるかい!!(笑) ラジオやったらとっくに放送事故やぞ!
私「あの~、前の方から電話の内容聞いてらっしゃらないんですか?」
担当者「あ、……少々お待ちください」
ふたたび保留、そこそこ長め。
担当者「お待たせしました、ご注文頂いたAとBのうち、Bが入っていなかったという事ですね?」
私「違います!!!!!! 」
二択問題か!? ○×クイズか!? しかもそれを外すか!?
実はこの後の展開で、彼女は更にヒドいクレーム対応をバシバシ決めてくるんですが(笑)今回のテーマがブレてくるんで、残りは後日にまわします。
目次
クレームの火種を大きくする、関連部署以外の従業員の接客対応
冒頭にも書きましたが、このケースが怖いのは、クレームを受け付けた担当者自身には、自分の応対のマズさで火種を大きくしているという自覚が起き難いという点です。
たとえば私が、二人目の女性に電話を代わった時にも自ら率先してクレームの経緯を話し出すタイプの人間だったら、今回のクレームはただの商品の入れ間違いとして終了しています。
その女性も最初の沈黙が起こった時点では「あれ? なんでこのお客さんは無言なんやろ」くらいの感じだったはずです。
当然のように私が自分から名乗って、用件について話し始めると思い込んでいました、ソレゆえの
担当者「………………………、え?」
なんですね(笑)
さて、ここからが本題です。
今回のケースで問題になるのは、二人目の女性の対応ではありません。
おそらくですが、彼女は電話を受けた時点ではクレームだと知らされていないと思われます。
上に書いた電話でのやりとりを、私の「ココロツッコミ」込みで読むと(笑)女性の対応に怒っているように見えますが、この状況を生んだ原因は一人目の対応によるものです。
テーマがブレるからと後半の経緯をカットしたのは、これ以降は完全に二人目の女性の問題になるからなんです、最終的にはふたりともアカンかったというね(笑)これはもう完全にこの会社の従業員教育の問題。
実は、私が二人目の女性に電話を代わった時に、私のほうから再びクレームの経緯について話し始めなかったのは「わざと」です。
電話を担当部署にまわされるなんてよくある事です、いつもの私なら電話の転送先でもう一度同じ話をするくらいは何でもありません。
今回「わざと」そうしなかったのは、決して私の底意地の悪さからではありません、その時すでに一人目の対応に充分イラついていたからなんです(笑)
クレームの電話を「商品スペックの問い合わせにでも対応してるつもり?」ってテンションで対応された挙句、謝罪どころか「ソレ、うちの担当じゃナイんで」感満点で電話を他にまわされたからです。
トドメの「はい、お電話代わりました●●です」のニュアンスと保留時間の短さで、一人目の男性はこの女性に「お客さんから電話やで~」程度の伝達しかしてないのがわかったから、もうこの会社のヤツらに同じ話を二回するのがバカらしくなったんです。
一人目の若い男性、言い方や聞き方にもいろいろ難はありましたが、それらの根本となる問題はひとつです。それは
「会社にかかってきたクレームを、自分に関係する出来事だという認識がない」
ということです。
重ねて言いますが、これは彼個人の資質ではなく、会社やお店での人材教育の問題です。
・お客様商売や顧客心理についての共通認識を教育していないというカリキュラムの問題
・お客様との関係性を定義する経営理念、ミッションが存在しないか、機能していない
・営業、カスタマーセンター、総務など各部署での「作業」が仕事のすべてだという間違った認識とセクショナリズムの問題
これらの問題を抱えるお店や会社では、陰で必ず発生しているであろう問題です。
スポンサーリンク
たとえば、わざわざクレームの電話をしてくるお客様の精神状態ってどういうものでしょう。
基本、怒ってますよね(笑)怒ってるか困ってる、または言ってあげるのが善意だと思ってます。
ムカついてる、イライラしてる、自分の状況を伝えたいと思ってる、共感して欲しいと思ってる、謝って欲しいと思ってる、すぐ解決して欲しいと思ってる、代わりの商品が明日までに欲しいと思ってる、返金して欲しいと思ってる、こんな気持ちを何とかして欲しいと思ってる、感謝してくれとは言わないが進言したことに対してはねぎらいの言葉くらいはかけて欲しがってる。
こういう方がしてくる電話、それがクレームです。
カスタマーセンターが存在していて、お客様からの電話はそこにしか行かない仕組みを作っているなら問題はありません。
けど、そんな会社は規模的にも事業形態的にもほんの一握りです。
目に付いた番号目指してお客様は電話しますので、クレーム内容とは関係ない部署にかかる可能性もありますし、先月入った新入社員がとる可能性もあります。
カスタマーセンターのベテランが電話に出ても、まったく畑違いの部署の新人さんが電話に出ても、お客様には関係ありませんよね。
関係ないというか「知ったこっちゃナイ」んです、誰が出るのかなんて。
お客様にとっては、電話に出た人が「会社の代表」なんですから。
ただでさえ不安や怒りを抱えたお客様の初期対応を、入ったばかりの新人さんや、クレーム内容とは関係しない他部署の人間が「会社の代表」として行わなければならない可能性があるわけです。
クレーム対応教育以前に必要な、経営理念や企業ミッション浸透
こうしたお客様の心理状態や、そもそも会社やお店がお客様とどういう関係を築きたいかという組織のミッションを理解していない人間が「組織の代表」としてクレームを受けると、お客様はどうなるか。
私のようになるわけです(笑)
消火どころか火に油を注いで「二度と買うか!!」と思わせてしまうわけです。
しかも多くの場合、その電話を受けた当事者は自分の対応に非があるという自覚がありません。
ヘタすれば「妙に怒ったお客様(笑)からの電話があった」としか思えないんです。
何ならこの場合「さっき変な客からの電話受けちゃってさぁ~」みたいな、さもお客様に非があるような認識のまま、社内の「雑談」で処理されて終わりになります。
常識があって勘のいい、センスや経験のある従業員ならどんな状況でクレームを受けても上手く対応するでしょうが、それってただの「ラッキー」でしかありません。
そういう人だけがお客様と接する仕組みになっているなら問題はありませんが、実際にはそうではないですよね。
畑違いの部署の人間や、研修も終わっていない新人さんが受けることだってあるわけです。
「オレ製造の人間だから、入れ間違いのことなんて知らんよ」
なんて思ってる従業員が電話をとっても、お客様の状況を理解し、適切な言葉をかけた上で担当部署にまわし、電話の保留中に状況を正しく伝えるルールが必要なんです。
これって個々のスキルでもなんでない、組織としての人材教育の問題です。
お店など対面接客の場では、昨日入ったアルバイトが接客しても店長が接客しても、お客様にとってはその人の印象が「お店の評価」になりますよね。
トレーニング不足で新人さんがミスして、しかも同僚が誰もフォローせずにほったらかしだと、そのお店の印象は最悪なわけです。
間違っても「また来ますね」なんて言ってくれませんよね、この瞬間に貴重なお客様を一人「殺してしまっている」わけです。
社屋で電話を通してしかお客様と接する機会がない従業員にだって、それは同じことなんです。
仕事を教える前に、お客様との関係性を理解させる制度や仕組みを社内に用意しよう
あのね、お客様をつぶす接客対応をする可能性のある人間は、お客様と接触させちゃダメなんですよ!
新人だとか部署が違うとかどうでもいいんです、お客様には。
誰が電話をとっても、それがお客様である以上は、お客様のおかれた状況や心理状態に寄り添って対応しないと、お客様は逃げます。
対面ではない、声を通してしか情報のやりとりが出来ないという限定的な状況だからこそ、一度誤解を生むとリカバー出来ないところまで一気に崩れます。
よく「クレームは、対応次第ではお客様がこれまで以上にお店や会社のファンになってくれる可能性があるチャンスでもある」なんて言いますよね。
これって事実です。
ホントにそうなりますし、私自身も何度も体感しています。
ただ逆に考えると、それくらいクレーム対応には、お客様の印象を劇的に好転も悪化もさせるポテンシャルがあるということです。
もう一度言います。
「お客様をつぶす接客対応をする可能性のある人間は、お客様と接触させちゃダメなんです」
これを回避するもっともシンプルな方法は、あなたのお店や会社にとっての「お客様とは何か?」という商売や事業の根本や存在意義を、すべての従業員と共有する仕組みを社内に用意することです。
キャリアもセクションを超えて、仕事を覚えるより先に、お客様とお店や会社との関係性を理解させる制度や仕組みを考えてみましょう。
【潰れないお店を手に入れたい方限定!】
店舗ビジネスは「来店客のリピーター化」が成功の鍵を握っています。お客様に「また行きたい!」と思われないお店が、商圏内で商売を続けることは不可能なのです。
・地域で愛され、永く繁盛が続くお店を経営したい方
・店舗ビジネスでの独立・起業を考えている方
・現在経営しているお店を根本から改革したい方
インパクトマーケティングの【店舗ビジネス「売れ続ける仕組み」構築マニュアル】は、商圏内のお客様を最大限リピーター化し、地域に根差して永く繁盛が続くお店の仕組みを構築します。売れ続ける仕組みと、優秀なスタッフが集まり育つ風土を作ることで、圧倒的な地域一番店を実現します。
もしあなたが、地域の方々に永く愛される繁盛店を本気で作りたいのなら、ぜひ導入をご検討ください。