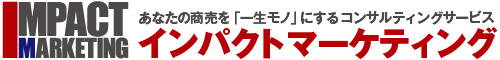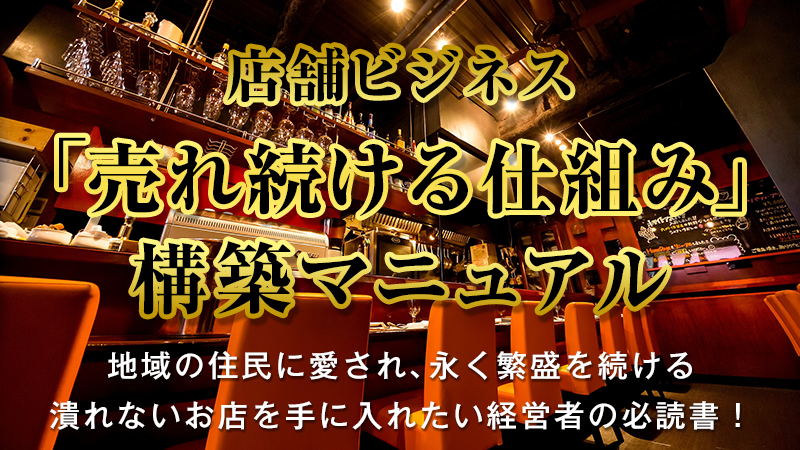ロゴの効用 その3 誰がお父さん犬やねんっ!?
どもっ!商売力養成コンサルタントの福谷です。
飛び石で二回にわたってロゴマークについてお話しましたが、ひとまずこれが最終回です。
今回は、自分のロゴを持つに当たっての注意点についてお話します。
名刺、看板、ホームページ、封筒、作ったロゴをどこでどのようにして使うかを想定して、その全てにおいて思惑が反映されるように注意する必要があります。
チラシのようにカラーで印刷される場合とモノクロで印刷される場合が考えられるのなら、単色刷りでもイメージを損なわないようにデザインしなくてはなりません。
社名や事業所名をそのままロゴとしてデザインする場合もありますし、シンボルマークとして別のモノを用意する場合もあります。
ロゴマークはあくまでも販促ツールです。
特に初めて自分のロゴを作る時は、テンションが上がりぎみになり(笑)仕事への想いや好みをおもいっきり形に反映させてしまいがちになります。
しかし、実際に使用するシチュエーションを考え、そこで販促ツールとしての機能を保持出来ているかという事を確認しながら作業を進めないと、ただの自己満足に陥ってしまう危険があります。
例えば色に関して、あくまでも一例としてですが、考え方の参考になるのはソフトバンクのロゴです。
ご存知のように数年前にボーダフォンを買収し、ソフトバンクという名前に変更しています。
あなたの近くのボーダフォンショップの看板も新しくなったと思います。
その当時、ボーダフォンの看板がソフトバンクに代わった頃の看板、見てどう思いましたか?
私の最初の印象は、「葬儀屋か?」でした(笑)
店の看板全てが、赤から「白を基調にグレー・黒」に変更された県道沿いの独立店舗を見た時、正直、「あ、こんな幹線道路に葬儀屋が出来たんや」と思ってしまいました。
しかし、結果的に言うと、このロゴの配色は大成功だと思っています。
理由は、何といっても、「色」です。
単体であのロゴを使用した看板等を見ると、「地味で味気ない」という印象を持つと思います。
しかし、ありとあらゆる色にまみれた街中であの看板を見ると、逆に目立つ事間違いありません。
それどころか、「シックで上品、センスいい!」とすら映るでしょう。
無いんです、あの色使いの看板って他に。
多くの人は目立つ為には強い色を使わなきゃと思っていますし、カラーでも作れると聞けばどうしても色を入れたくなります、入れなきゃ損とばかりにいろんな色を投入してきます(笑)
結果的にはどうしても「カラー偏重主義」になるんですね。
以前のブログにも書いたように、「飲食店なら赤と黄色」みたいな既成概念・カラーマネージメントが存在する事も一因でしょう。
以前立ち読みした(笑)DTP関係の雑誌に載っていた調査では、ロゴマークに使用されている色のパーセンテージが以下のようになっていました。
(但し、何せ立ち読みだったので数値は若干アバウトです)
赤 50%
青 35%
緑 8%
黄 5%
その他 2%
例のカラーマネージメントで、業種別での数値はまた大きく違うと思いますが、白・グレー・黒というモノトーンって、実は非常に少ないんです。
ソフトバンクの場合、圧倒的なCM露出で半ば腕ずくでねじ伏せて世間に浸透させたという感もありますが、少なくとも配色に関して言えば見事と言うしかありません。
既成の販促理論を鵜呑みにせず、お客様が目にする環境・販促ツールが置かれる環境を観察し、一番効果的な方法を採用する。
ロゴマークを「大事に守る実印的伝統」とは捉えず、販促ツールと位置づけする以上は、このインパクトマーケティング的考え方を加味して、デザイン・色にこだわって頂きたいと思います。
念の為に言っておきますが、この例は「ロゴはモノクロで作りなさいよ」と言ってるわけでは決してありませんので誤解しないで下さいね(笑)
スポンサーリンク
さて最後に、ロゴを作成したくなった・変更したくなった方の為に簡単なガイドを。
まず、作成をプロに頼む方。
懇意にしているデザイナーさんがいるのであれば、その方にお願いするのもいいでしょう。
融通が利く、というのは大きなメリットです。
そういう人がまわりにいないのであれば、どこかのデザイン事務所にお願いする事になるのですが、注意点がいくつかあります。
まず、デザイン価格というのは相場こそありますが、基本的に「言い値」です。
予算が限られている場合は、まずこちらが望む条件をちゃんと伝えて、合い見積りを取るくらいで行きましょう。
値段が高いから良いものを提供する、という判断は禁物です。
また、デザイナーにはそれぞれ「得意分野」があります。
「注文は受けるけど、正直ロゴ作成は得意じゃない。」という人もいますので、正面きって「得意ですか?」と確認する事や、過去のデザインを見せて貰う事は必要です。
そして、これが実は非常に大事なんですが、絶対に忘れてはいけない事があります。
販促ツールを作る為に商売人とデザイナーが接する機会が多いので、今までもこれからも私は事あるごとに何度でも声を大にしていい続けます(笑)
それは、「デザイナーは商売人ではない」という事です。
多くのデザイナーが考える「売れる広告、売れるPOP」というのは、あくまでも広告業界・デザイン業界での常識を基にしたものです。
要するに、前述した「飲食店なら赤と黄色」という常識と、カッコいいデザインに囚われている人が大勢いるんです。(もちろん、そうじゃない人もいますが)
売る為の設計図、売り方のデザインをするのはあなたです、デザイナーではありません。
あなたがデザインした売り方をビジュアル化するのがデザイナーの仕事です。
デザイナーが口にする「デザインあるある」なんて聞いてはいけません(笑)
「デザイナーは、俺の考えをビジュアルで表現する為だけに雇う」というスタンスで臨んで頂きたいと思います。
そうでないときっと、提示されたカッコいいだけのヘボデザインに流されてしまうでしょう。
さて、近くにデザイン事務所が無い場合はネットで注文しましょう。
「ロゴ作成」で検索すれば、ロゴ作成を専門としているサイトがいくつもあります。
価格も明示していますので、どのくらい融通が利くのかと併せて考えましょう。
コンペ形式で複数の人がデザインを提案してくれるサイトもいくつかあります、プロも素人も混在していますが、いろんな提案の中から選びたいのであればお勧めです。
次に、自分で作成する場合。
本格的にやってみようと思われるのであれば、有料のソフトになるでしょう。
アドビ社のイラストレーター、フォトショップなどが代表的なソフトになります。
但し、高いです(笑)
ロゴを外注する方が安くつきますので、ロゴ作成の為だけに購入しようと思っているのであれば、お勧めしません。
しかしどちらのソフトも商業印刷用の原稿を作成出来ますので、ゆくゆくは自分で本格的なチラシやPOPをデザインして、製作だけを外注したいという考えがあるのならお勧めです。
ホームページやブログをお持ちの方にとっても、バナーやボタンなどの素材を作れますので、「元がとれる」と思うのであればお買い求めください。
「そこまで投資は出来んがな」という方、商業印刷をしない範囲であれば、とりあえず無料のソフトで充分です。
上記アドビ社のイラストレーターやフォトショップに近い機能を持った、オープンソースのフリーソフトがネットから入手出来ますし、有名なモノなら使い方のムックが出版されていたりファンサイトで解説されていたりします。
とにかく、「ロゴはあった方がいいっ!」って事です(笑)
【潰れないお店を手に入れたい方限定!】
店舗ビジネスは「来店客のリピーター化」が成功の鍵を握っています。お客様に「また行きたい!」と思われないお店が、商圏内で商売を続けることは不可能なのです。
・地域で愛され、永く繁盛が続くお店を経営したい方
・店舗ビジネスでの独立・起業を考えている方
・現在経営しているお店を根本から改革したい方
インパクトマーケティングの【店舗ビジネス「売れ続ける仕組み」構築マニュアル】は、商圏内のお客様を最大限リピーター化し、地域に根差して永く繁盛が続くお店の仕組みを構築します。売れ続ける仕組みと、優秀なスタッフが集まり育つ風土を作ることで、圧倒的な地域一番店を実現します。
もしあなたが、地域の方々に永く愛される繁盛店を本気で作りたいのなら、ぜひ導入をご検討ください。